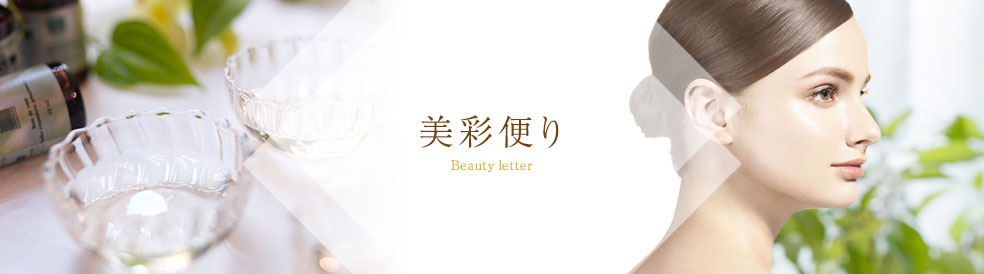冬の寒さが厳しくなってきてきましたが、二十四節気ではいよいよ「冬至」を迎えます。 冬至とは1年間で最も夜の時間が長い日となるので、毎年必ず同じ日ではありません。 今年2017年は12月22日が冬至ですが、去年は12月21日でした。これは「うるう年」が関係していて、通常は12月22日になりますが1日多くなるうるう年では12月21日となるのです。 ただ、1955年

各地で雪の積雪が観測し始める今の時期を七十二気候では鱖魚群(さけのうおむらがる)と言い、鮭が群を作り川を上っていく様を指しています。鱖魚は「ケツギョ」とも言い、本来は中国に生息している、スズキ目に分類される淡水魚で川を群れて泳ぎます。日本にはいない種のため、中国暦が日本へ伝わる際に同じく川を群れて泳ぐ鮭が充てられて、そう読まれるようになったそうです。 さて、本

12月に突入し、いよいよ今年も残りわずかとなってきました。 この時期を七十二気候では、橘始黄(たちばなはじめてきばむ)と言います。 冬は柑橘系の果物が旬を迎える時期で、柑橘類のひとつである橘が黄色く色づき始めることからこう呼ばれるようになりました。 こたつに入ってみかんを食べる光景は日本の冬の風物詩ですよね。そして、年末に向けて慌ただしくなるとともに体調を崩す

静電気と体調の関係 11月も終わりに近づき、今年もあと1か月を切りました。七十二候では、この時期を「朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)」と呼びます。 北風が吹き、落葉樹の葉を吹き飛ばし、枝には何も残らない状態になり始める時期です。 この時期、日本海側では日本海から湿った空気が流れ込み雪が降り、太平洋側では逆に乾燥した空気になるため、乾燥注意報がしばしば出されま

寒さと乾燥が進み、本格的な冬が訪れました。 七十二候では、この時期を「金盞香(きんせんかさく)」と呼び、水仙という冬から春にかけて咲く花が咲き始めるころとされています。 街はイルミネーションで華やかに彩られ、年末に向けて心がうきうきと浮足立つ方も多いことでしょう。 しかし、この時期からはインフルエンザや風邪が流行し始めます。 そんな風邪予防に効果があるといわれ

木々が鮮やかに色づき、木枯らしが吹き、地域によっては初雪が観測されるなど、いよいよ本格的な冬に向けた準備の時期が訪れました。 七十二候では、冷たい空気によって地面が凍り始める季節という意味で、この時期を「地始凍(ちはじめてこおる)」と呼びます。 この頃になると、冬の風物詩でもあるこたつを出し始める家庭が増え、コートやニットを着て冬のファッションを楽しむ姿も見ら

ついに11月となり、今年も残すところわずか二カ月となりました。 今の時期は七十二候では「楓蔦黄(もみじつたきばむ)」と言い、葉が赤や黄色に色付くようになります。 赤・黄・緑の色が一度に楽しめるのは世界でも珍しく、美しい紅葉を目当てに毎年海外から多くの観光客が訪れるほどです。 そんな自然の景色が美しくなるこの時期に気を付けたいのが、体の内側、特に「肺」の乾燥です

天気が悪い日が続き、気温も下がりやすくなっていますね。 ぱらぱらとした雨が降ったり止んだりを繰り返しながら、少しずつ気温が下がり、冬に向かっていくこの時期を、七十二候で「霎時施(こさめときどきふる)」と呼びます。 晩秋特有の雨が降り出したと思ったらすぐに青空になるという現象は、大陸から冷たい空気が流れ込み、それが日本近海で温められて小さな雲がいくつも発生するこ

秋が深まり、朝晩の冷え込みが一段と厳しくなってきました。 この時期は、冬の訪れを告げる七十二候の一つ「霜始降(しもはじめてふる)」と呼ばれます。 気温が下がると、空気中の水蒸気が氷の結晶となり霜が降ります。 霜は古くから冬の風物詩として親しまれ、俳句などにも詠まれてきました。 早朝、畑や草花に降りた霜がキラキラと輝く様子は、まさに自然の美しさを感じさせます。

秋も深まり、七十二候では「菊花開(きくのはなひらく)」という時期になりました。 菊の花が見ごろを迎えるこの時期、日本各地で菊の展覧会や品評会が開催され、多くの人々でにぎわいます。 菊は桜と並んで、古くから日本の秋を彩る花として大切にされてきた国花です。 栄養豊富で、不老長寿の薬とも言われ、菊花酒という菊の花をお酒に浮かべて飲む風習もあり、まさに「見てよし、食べ