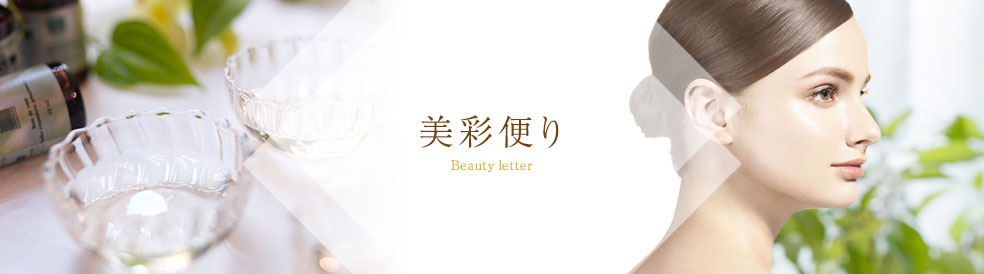2018年も一週間が過ぎ、今日から本格的に仕事始めだったという方も多いのではないでしょうか? 今の時期を七十二候では、「芹乃栄」(せりすなわちさかう)と言い、セリが成長する時期を指しています。セリと言えば、「春の七草」に入れる草花として有名ですよね。 お正月最後の日、1月7日に無病息災を願い七草粥を食べますが、本来は五節句という季節の変わり目のひとつ「人日の節

明けましておめでとうございます。ついに2018年を迎え新しい1年が始まりました。 新年最初の七十二候は「雪下出麦」(ゆきわたりてむぎのびる)と言い、雪が降る降り積もる中、麦の芽が少しずつ伸び始める時期とされています。 麦は二年植物で、種を撒いてから年内に収穫できる一年植物とは違い、冬を越して春~夏に収穫をする種類のため、越年草(えつねんそう)とも呼ばれています

今年も残すところ1週間を切り、間もなく2017年が終わりを告げようとしています。 今の時期は七十二気候では「麋角解」(さわしかつのおる)と言い、大鹿の角が落ちる時期だとされています。 しかし、日本にいる鹿の角が落ちる時期は春で、今の時期ではありません。どうして今の時期に鹿の角が落ちるのでしょうか? これには諸説ありますが、中国では神獣とされ今では野生絶滅と

冬の寒さが厳しくなってきてきましたが、二十四節気ではいよいよ「冬至」を迎えます。 冬至とは1年間で最も夜の時間が長い日となるので、毎年必ず同じ日ではありません。 今年2017年は12月22日が冬至ですが、去年は12月21日でした。これは「うるう年」が関係していて、通常は12月22日になりますが1日多くなるうるう年では12月21日となるのです。 ただ、1955年

寒さと乾燥が進み、本格的な冬が訪れました。 七十二候では、この時期を「金盞香(きんせんかさく)」と呼び、水仙という冬から春にかけて咲く花が咲き始めるころとされています。 街はイルミネーションで華やかに彩られ、年末に向けて心がうきうきと浮足立つ方も多いことでしょう。 しかし、この時期からはインフルエンザや風邪が流行し始めます。 そんな風邪予防に効果があるといわれ

天気が悪い日が続き、気温も下がりやすくなっていますね。 ぱらぱらとした雨が降ったり止んだりを繰り返しながら、少しずつ気温が下がり、冬に向かっていくこの時期を、七十二候で「霎時施(こさめときどきふる)」と呼びます。 晩秋特有の雨が降り出したと思ったらすぐに青空になるという現象は、大陸から冷たい空気が流れ込み、それが日本近海で温められて小さな雲がいくつも発生するこ

秋が深まり、朝晩の冷え込みが一段と厳しくなってきました。 この時期は、冬の訪れを告げる七十二候の一つ「霜始降(しもはじめてふる)」と呼ばれます。 気温が下がると、空気中の水蒸気が氷の結晶となり霜が降ります。 霜は古くから冬の風物詩として親しまれ、俳句などにも詠まれてきました。 早朝、畑や草花に降りた霜がキラキラと輝く様子は、まさに自然の美しさを感じさせます。

9月も中旬を過ぎ、本格的な秋がやってきました。 七十二候では玄鳥去(つばめさる)と呼ばれ、渡り鳥のツバメが夏の終わりとともに子育てを終え、暖かい南へと帰っていく季節です。 この時期は気温の急激な変化があり、空気の乾燥が激しくなります。 すると、肌に負担がかかり、カサカサして艶がなくなり、さらにシワやシミ、たるみが目立つようになってしまいます。 そんなお疲れ肌の

明日、8月24日は二十四節気の「処暑」にあたり、暑さが和らぐ日とされています。朝晩は少しずつ涼しくなる一方で、日中はまだ暑さが残るこの時期、特に注意したいのが「肌の老化」です。この時期は、紫外線によるダメージが蓄積されているうえ、温度差が激しいため、体が変化に追いつけず、疲れやストレスを感じやすくなります。その結果、乾燥肌が進行しやすく、シワやシミ、たるみがで